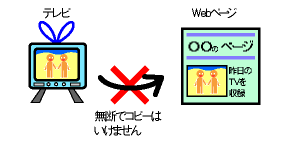実演家やレコード製作者、放送事業者などは、「著作物の伝達者」としての役割を果たす意味で、著作権とは別に著作隣接権という権利で保護されています。それぞれの著作隣接権は、放送権、送信可能化権、譲渡権、貸与権、複製権などから構成されます。もちろん著作隣接権を得るためには、著作権者の許諾が必要です。
■ 改正著作権法
2012年6月、著作権法の一部改正する案が国会で可決されました。違法ダウンロードの刑罰化とDVDリッピングの違法化が主な改正点です。
これまで、違法にアップロードされた音楽や映像を違法と知りながらダウンロード(録音または録画)する行為については、私的使用の範囲では、違法としながらも罰則は設けられていませんでした。
今回の改正において、「有償の著作物」を違法と知りながらダウンロードする行為について、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科あり)と規定されました。
また、DVDなどに用いられる暗号を解除して複製する行為(リッピング)についても違法となりました(刑事罰はなし)。
違法ダウンロードの刑罰化とDVDリッピングの違法化に関する規定は、2012年10月1日から施行されました。
なお、写真や動画に写り込んでしまった他人の著作物については著作権侵害とならないともされました(2013年1月1日施行)。
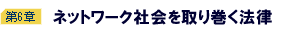
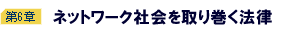
 動画違法配信:ネット倉庫を悪用 容疑で少年6人書類送検
動画違法配信:ネット倉庫を悪用 容疑で少年6人書類送検