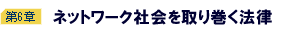
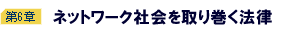 |
| 6-3 | 著作権侵害行為と罰則 |
| 著作権法に違反しないためには、他人が作成したものを無断で使用しないことが原則です。他人の著作物を複写、引用したり、Webページなどに掲載したいときは、「許諾の必要がない」と認められているもの以外は、必ず許諾を取る必要があります。 従来、国際的な著作権の保護の枠組みとしては、1886年に締結されたベルヌ条約がその役割を果たしていました。ただしベルヌ条約は、紙などに印刷されたりテープなどに録音されたりする製作物に対する著作権保護の取り決めで、デジタル化された著作物は、この条約だけでは保護しきれなくなっています。 |
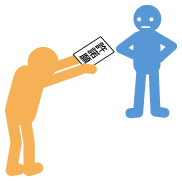 |
| デジタルデータは、アナログデータと違って質の劣化を伴わずに大量に複製できるなどの特徴があります。つまり、デジタルデータにはオリジナルとコピーの相違点がないのです。
ネットワーク上で配布、販売されれば、著作権者が大きな損害を受けることになります。
ところが、ベルヌ条約はデジタルデータの著作物を想定していないので、現在のデジタル化の時代にそぐわなくなりました。 そこで、1996年12月、WIPO(世界知的所有権機関)で、著作権に関する世界知的所有権機関条約(略称:WIPO著作権条約)と、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(略称:WIPO実演・レコード条約)が採択されました。これに合わせて、日本でも1998年に改正著作権法が施行され、インターネット上での著作権について、次のような取り決めができました。
また、家庭などでデジタル方式の音楽や映像を記録する場合に、著作権者に補償金を支払う制度(私的録音録画補償金制度)が定められています。実際に支払っているという感覚はありませんが、デジタル方式で記録する機械やメディアを購入する際、代金の一部に含まれています。 |
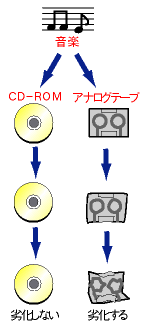 |
ソフトウェアのライセンス契約とは、ソフトウェア使用許諾契約のことです。インストールできるパソコンの台数や使用期間などが決められていますので、ライセンス契約の内容にしたがって利用しましょう。無断でコピー、配布すると処罰の対象となります。
なお、契約方式の代表的なものには以下の3つがあります。
インターネット上では、以下のような行為は、著作権の侵害にあたり、禁止されています。十分に気をつけましょう。
| 違法な掲載・アップロード(犯罪となります) |
|---|
|
| 違法なダウンロード(犯罪となります) |
|---|
|
以下は日本の著作権法で定められている主な罰則です。上の著作権侵害行為と照らし合わせて、どの行為がどの罰則にあたるか考えてみましょう。
| 条数 | 内容 | 罰則 |
|---|---|---|
| 第119条1項 | 著作権、著作隣接権を侵害した者 | 10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(併科あり) |
| 第120条 | 著作者や実演家が死亡した後の著作者人格権を侵害した者 | 500万円以下の罰金 |
| 第120条の2 | 技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置・プログラムなどを提供することに関わった者 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科あり) |
| 第121条 | 著作者でない者の実名または周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物を頒布した者 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり) |
| 第121条の2 | レコードの頒布権を持たないで、商業用レコードを商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、またはその複製物を頒布の目的をもって所持した者 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり) |
| 第122条 | 著作物の出所を明示しなかった者 | 50万円以下の罰金 |
グーグル社による「図書館プロジェクト」とは、欧米の図書館と提携し、蔵書の全文をデジタル化する計画のことです。このサービスにより、グーグルの「ブック検索」で、誰でも書籍データベースを利用することができます。
米国の作家団体などが、著作権者に無断でデータベース化を進めたとして、グーグルを著作権法違反で訴えましたが、その後著作権者とグーグル間での和解が進み、電子化がさらに進められています。
日本でも、2009年に国立国会図書館が所蔵する和書を電子化してインターネットで配信することを発表しました。現在32万冊が閲覧できます。
書籍を裁断し、スキャナでデジタルデータに変換することを「自炊」といいます。自分で電子化したデータをタブレット端末などで個人的に利用するのはかまいませんが、知人にデータを譲渡したり、ネットオークションなどで販売すると著作権法違反となります。