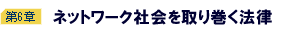
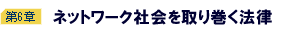 |
| 6-9 | 特定電子メールの送信に関する法律 |
多数のユーザに対して同時に送信される広告メールを「特定電子メール」といいます。単に広告や宣伝として使われる場合もありますが、最近では詐欺行為の種としてばらまかれる場合があります。関心のないものを受信させられたり、うっかりすると詐欺に巻き込まれたりするため、このようなメールは「スパムメール」と呼ばれ、インターネットを使った迷惑行為のひとつとなっています。
そこで、このようなメールによるトラブルを防止するため、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」、いわゆる「迷惑メール防止法」が2002年7月から施行されています。以降、フィッシング詐欺やワンクリック詐欺など、電子メールを利用した犯罪が増加していることから、取り締まりを強化する目的で2005年と2008年に一部が改正されています。特に、2008年の改正では、オプトイン方式(メール配信についてあらかじめ受信者の同意が必要)の導入、一部罰金の大幅引き上げ、海外から発信される迷惑メールの規制などが含まれました。
「特定電子メール」を送信する場合、送信者は、以下の事項をはっきり表示するよう義務づけられています。
よって、以下のような行為をすると改善命令が出され、それに従わないときは犯罪となります。
また、特定電子メールの送信について、受信者側の同意を得ているという記録を保存する義務もあります。
 迷惑メール:初の改善命令--総務省
迷惑メール:初の改善命令--総務省